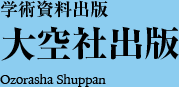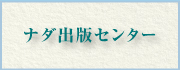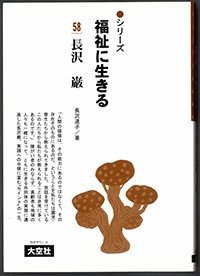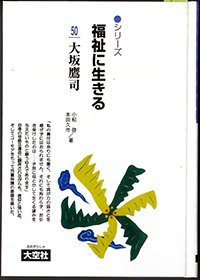福祉・医療
シリーズ福祉に生きる59 グロード神父
発行年月:2011年2月(大空社刊)
(フィリッポ・グロード Philippe Gourraud 1927・昭和2~2012・平成24年) 1954・昭和29年、フランス人宣教師として来日、北海道函館の地に〈尊厳をもって生きる〉「高齢者人権憲章」の理念のもと、高齢者施設を開設。また、日仏親善や函館野外劇創始など、地域活性化にも貢献。国境を越えて信仰と市民の協力に支えられる社会福祉の幸福な結実をみる。
シリーズ福祉に生きる58 長沢巌
発行年月:2010年10月(大空社刊)
(ながさわ・いわお 1927・昭和2~2007・平成19年) 「人間の価値は、その能力にあるのではなくて、その存在そのものにあるのだ、ということを私たちは園児・寮生たちから教えられてきました。世話を受けているこの人たちから私たちが教えられることは非常に多くあるのです。」障がい者のみならず、高齢者も地域の人々も一緒になって、共に生きる共同体の実現に邁進した。実践への示唆に富む「セイント」の一生。
シリーズ福祉に生きる57 近藤益雄
発行年月:2010年10月(大空社刊)
(こんどう・えきお 1907・明治40~1964・昭和39年) 「平和なくしてこの教育もなく、この子どもたちのいのちもないということをおもう。人間のねうちを、ほんとうに平等に大切にする世の中であるならば、きっと平和がまもられるにちがいない。この子どもたちも完全にまもられるにちがいない。」戦後の長崎で、知的障がい教育・福祉の実践家として、家族ぐるみで苦闘した詩人教師。知的障害児生活教育施設「のぎく寮」創設。
シリーズ福祉に生きる56 森章二
発行年月:2009年6月(大空社刊)
(もり・しょうじ 1943・昭和18~2010・平成22年) 「高齢化社会のなかで、保健・福祉・医療の連携を密にして、当事者の要望に即座に対応できるシステムの構築が緊急かつ不可欠である」筋ジストロフィー症を背負いながら、障害者の連帯活動、車いす市民集会の開催などに奔走、福祉のあるべき姿を先取りして追求してきたのは「自立」への道である。
シリーズ福祉に生きる55 江角ヤス
発行年月:2008年11月(大空社刊)
(えすみ・やす 1899・明治32~1980・昭和55年) 「殉難純女学徒隊員の方々へのせめてものお供えのつもりで、老人ホームを建設して、孤老の方たちに純心の子らの奉仕を…」純心高等女学校校長の身で長崎原爆投下に遭遇。校舎の下敷きになりながらも生き残り、殉難学徒たちの供養と「純心教育」の復興、被爆者福祉施設を創設等、教育・福祉事業に一生を捧げた。
シリーズ福祉に生きる54 若月俊一
発行年月:2008年11月(大空社刊)
(わかつき・としかず 1910・明治43~2006・平成18年) 「どんな正しい理論も、それが民衆と結びつかなければ物質的な力とはなりえないのだ」治療一点張りの医学のあり方を批判し、予防と健康管理の重要性を説いて地域医療に新しい一頁を切り開く。長野県の佐久病院院長として五十年にわたり農村医学を実践し、これを日本だけでなく世界的にひろめた、農村医学・地域医療の父。
シリーズ福祉に生きる53 姫井伊介
発行年月:2008年11月(大空社刊)
(ひめい・いすけ 1881・明治14~1963・昭和38年) 「失業対策事業、失業保険制度の充実等が挙げられております。これで処理できない最期の段階は生活保護法ですが、それでも未だ不十分であります。…」昭和の初期、山口県政、参議院を舞台に、社会福祉の新時代を見据えて、粘り強く多様な活動を展開。広い視野と情熱をもって、まさに未知の世界を開拓した。
シリーズ福祉に生きる52 長谷川保
発行年月:2008年11月(大空社刊)
(はせがわ・たもつ 1903・明治36~1994・平成6年) 「私が言ってきたことは、絶えず前進しろと。日本の社会、あるいは世界、アジア、アフリカを見て、さらに何をやるべきか。これはキリストが聖書のなかで『貧しい者は、常にあなた方と共にある』と書いているからです。」揺るぎないキリスト教信仰を支えに、医療福祉全域に事業を展開、今に続く「聖隷」グループを築き上げた。
シリーズ福祉に生きる51 石井亮一
発行年月:2008年11月(大空社刊)
(いしい・りょういち 1867・慶応3~1937・昭和12年) 「信仰と愛、そして最新の科学の力、この三者なくしては到底この貴い使命を全うすることは出来ません。」日本の知的障害者教育・福祉は、石井亮一が蒔いたこの一粒の麦から、大きく生長したと言わねばならない。
シリーズ福祉に生きる50 大坂鷹司
発行年月:2001年11月(大空社刊)
(おおさか・たかし 1897・明治30~1971・昭和46年) 「私の責任は余りにも重く、そして我が力の弱さとを感ぜずにはおられません。それにも拘らず、お引き受けしたのは…子供に何とかして生くる望みを与えたいものと願うゆえであります」自身の苛酷な運命に翻弄されながらも、信仰と強い志、そしてユーモアをもって児童保護の基礎を築いた。