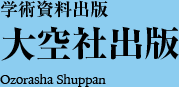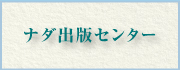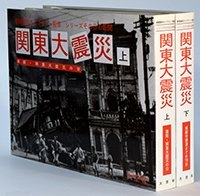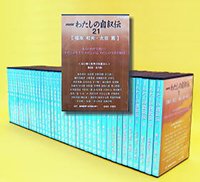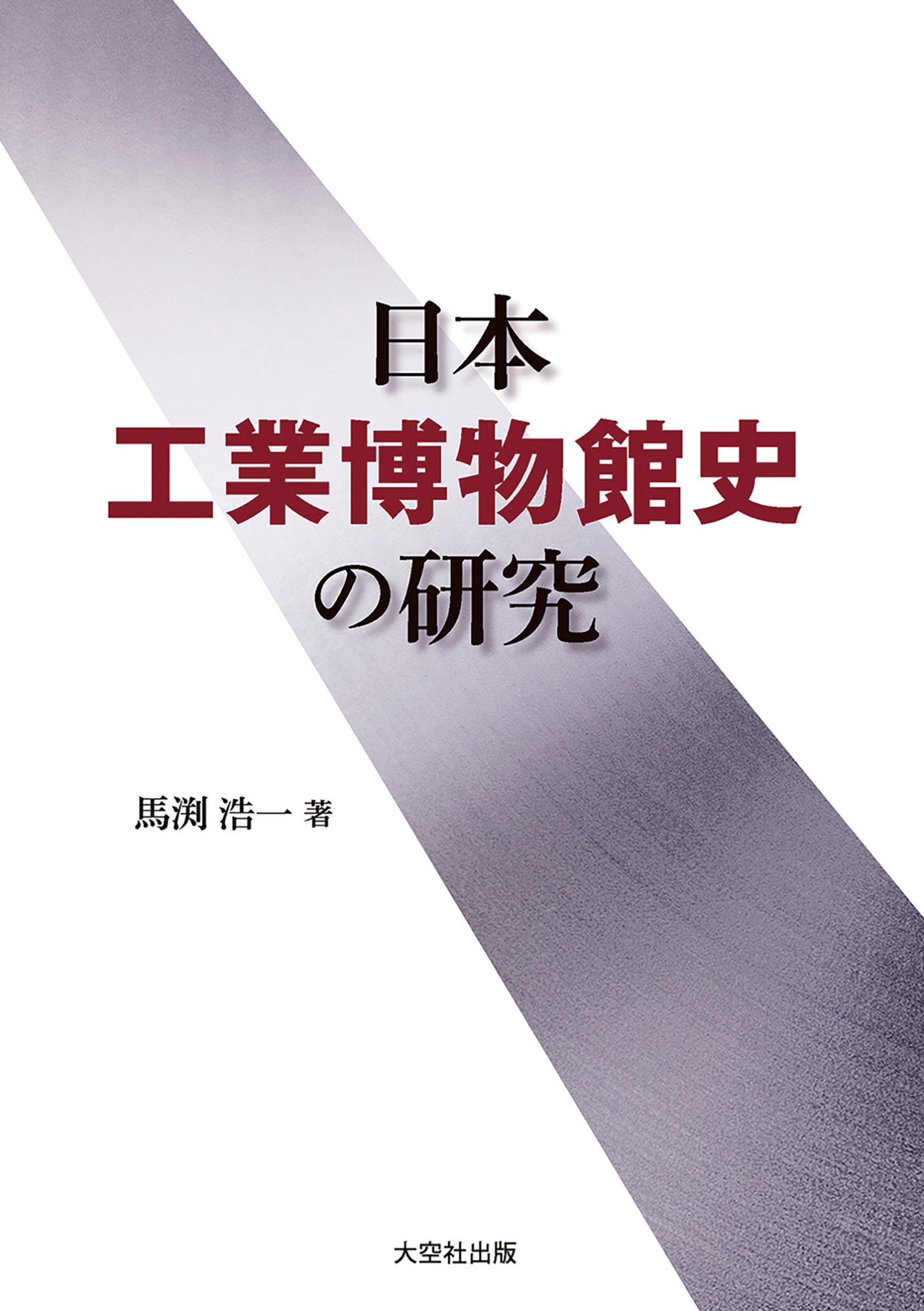近現代
〈シリーズその日の新聞〉関東大震災 全2巻
発行年月:1992年8月(大空社)
1923(大正12)年9月1日 関東大震災が起きた日から2か月半後、戒厳令が撤廃された11月16日までの全国の新聞(延べ37紙)・官報等を分類・整理し収録。
関東大震災がもたらした社会の変動が、迫力の紙面から手に取るように読み取れる歴史の第一級資料。
さながら当日の新聞を手に取るような迫真の紙面【大判(297×420ミリ)。広げればA2判の特大折込を多数収録】に、生々しく惨状が展開する。現在では制作困難な貴重な蔵本。
○お断り:本の状態について○本書は刊行年が古いため(約30年前)、カバー・表紙・見返し等に経年による劣化が見られますが、本文は良好で閲覧に支障はありません。
NHK わたしの自叙伝 CD全39枚・解説書1
発行年月:(2回配本)2012年5月・10月
★「戦後80年・昭和100年」のいま、あの人たちが「自らの戦争・戦中期体験」を語る貴重な音声記録!
昭和を代表する各界の巨星78人が音声で残した生涯の核心。
政治家・実業家・事業家・社会運動家・教育者・学者・研究者・ジャーナリスト・作家・芸術家・デザイナー・演劇人・映画人・俳優・スポーツ人。現代日本のさまざまな分野で活躍し名を残す“あの人”たちが、じっくりと自らを語る貴重な音声記録。
シリーズ福祉に生きる66 菊田澄江(再版)
発行年月:2025年8月27日刊行
●菊田澄江(きくた・すみえ 1906~1995)
栃木県足利に牧師・森田金之助の次女として生まれ、大阪で育つ。ウヰルミナ女学校(現・大阪女学院)、大阪府女子専門学校(後の大阪女子大学、現・大阪府立大学)英文科卒業後、ウヰルミナ女学校英語教師となる。戦中に夫を亡くし、三児を育てながら、銀座に進駐軍向けのナオミ洋装店を開く。1951年12月、財団法人ナオミの会設立〈現在、社会福祉法人ナオミの会:本部、東京都世田谷区等々力。「ナオミ」は旧約聖書ルツ記にある未亡人の名〉。1954年、東京・世田谷に、キリスト教精神にもとづく、職業訓練のための母子寮ナオミホーム、ナオミ保育園を設立。全国初の病児保育や、産休明け乳児保育・0歳児保育等にも先駆的に取り組み、生涯を母子家庭の自立・子育て支援のために捧げた。
●再版にあたって(抄)(2025年8月 終戦の日に 遠藤久江)
ナオミの会の歴史を考える時、どうしても第二次世界大戦後の日本の姿を描きながら進めなければなりません。2025年は戦後80年目を迎え、戦争による破壊や荒廃は過去のものとなり、忘れられてきていますが、ウクライナの戦争やガザ地区での戦禍の現実が80年前の日本の姿を髣髴とさせます。1945五年の敗戦は生き残った者たちにとっては過酷な現実を生きのびるための闘いの日々の始まりでもあったのです。ナオミの会はそのような状況の中から生まれました。
今日のナオミの会は1カ所の母子生活施設、4カ所の保育園(2カ所の分園)を持つ大きな組織になりました。
ここ数十年の社会の変化には目を見張るものがあります。高度に発展した社会経済状況は人々の生活を豊かにしていますが、一方で持てるものと、持たざるものの格差を拡大させ、高度に発達しているデジタル社会は生活の利便性は高まっていますが、人間同士の感情の交流を不要とし、孤立感と疎外感を深める結果をもたらしています。
このような社会がもたらす意識の変化や生活スタイルの変化は、若い子育て世代に一番早く現われます。保育者はこの現実に向き合って親たちと協働している専門家集団です。親の子どもへの思いはさまざまですし、大事にしたい思いも多様です。この親たちと地域社会の子育てをしているナオミの会を継承しているものたちは菊田先生の歩みから大切にするべきものを見出していかなければなりません。」
反骨の新聞人 長谷川善治 昭和初年『萬朝報』での言説と行動
2025年8月
長谷川善治――戦後80年・昭和100年のいま、この知られざる「新聞人・ジャーナリスト」の“火を噴く”言説に耳を傾けよ!100年前の日本・世界は、まさに現代の引き写しだ!
★初めてなる人物伝★
明治創刊の名だたる『萬朝報』(よろずちょうほう)の再興に尽くし社会問題摘発に果敢に挑んだ熱血漢の言説と行動の真意を読み込み冷静な歴史家の目で時代の中に位置づける。同時に、弟・長谷川良信―社会事業家・教育者・浄土宗大僧正―の『萬朝報』主筆としての活躍に初めて光を当てる。著者(善治の甥、良信は父)でこそ書けた記念的論考。
アジア学叢書 第53回配本「満洲Ⅱ編」全5巻(363~367巻)
発行年月:2023年9月
満洲国の建国・建設と教化・宣撫組織=満洲国協和会。貴重な歴史の証言から改めて移住・経営・視察・教育の実際を知る稀少資料を復刻。
【関連領域・テーマ・キーワード】満洲国建国・満洲国協和会 国策・宣撫 軍事・統治・植民地・民族 文化・風習 教育・視察旅行 牧畜・農業・自然 実録・目撃者・当事者・民衆意識
日本工業博物館史の研究
発行年月:2023年10月
明治以降、幾度となく提案されてきた日本の工業博物館設立計画、しかしいまだ実現されないのはなぜなのか?近代日本の博物館の歴史に刻まれる“工業博物館”構想に関わった官民・学術・教育の人々の営為を、厖大な史料文献・データを的確に整理し、鋭く歴史の核心に迫る。永年、博物館業務に従事してきた著者だからこその視点で書かれたユニークな業績。各種変遷・概要・分類・数量データから組織・人物略歴・社会背景を明解に提示する有益・豊富な図表54点を収載。読みやすい・明解な文章。
アジア学叢書 第52回配本「鮮満(朝鮮・満洲)編」全4巻(359~362巻)
発行年月:2022年8月
近代日本が関心を持ち続けた「鮮満」(朝鮮・満洲)
統治/被統治の関係と歴史、産業・経済・旅行・調査・視察、生活する日本人と他国の人々。
実体験記録が語る、遠く過ぎ去った時代へ開かれた資料群。
アジア学叢書 第51回配本「満洲Ⅰ編」全5巻(354~358巻)
発行年月:2022年4月
「満洲国」建国90年(建国1932・昭和7年)、13年の「帝国」、広大な地に築かれ、おびただしい人が渡って生活した…無尽蔵の資料はまだまだ語りつづける。ぎっしり詰まった文字情報と、多種多様な「地図」を収録。「満洲」研究に役立つ資料を精選!叢書待望の「満洲編」第一弾!
アジア学叢書 第50回配本「アジア巡り編」全6巻(348~353巻)
発行年月:2021年12月
“アジア”の東西南北・古今を縦横無尽に“巡り”廻って、いまとこれからに必要な資料を提供しつづけ四半世紀!“50 回”を画期として新たな「アジア巡り」へ出発!自然の景観・奇観、高地・低地、海・川・湖、熱帯・寒地・大都市・僻村、街並み・家並み、建築、寺院、動植物…なによりも、そこに生活する人間との接触・交流を通して、風物・習慣を、土地と社会の歴史に沁み込んだ文化を実体験した真実の記録集を精選して贈る!
〈史料復刻〉ビコール日本人會 會報 1931-1941(全2巻・別冊)
発行年月:2020年11月
真珠湾攻撃(1941・昭和16年12月)直前、内地に持ち帰られたまま数十年眠っていた「超一級」貴重文書を「鮮明」復刻!
「廃棄」の運命を奇跡的に逃れ、ここに現る!
類似史料ほぼ皆無!昭和戦前期の〈海外〉日本人会の実態を克明に伝える一級史料