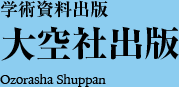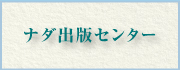シリーズ福祉に生きる66 菊田澄江(再版)
シリーズ福祉に生きる(編者:津曲裕次)
発行年月:2025年8月27日刊行
価格:2,200円(本体2,000円+税10%
ISBN:978-4-86688-242-0
体裁:B6判・172頁・並製・カバー装
特記:初版2014年5月の修訂第2刷

●菊田澄江(きくた・すみえ 1906~1995)
栃木県足利に牧師・森田金之助の次女として生まれ、大阪で育つ。ウヰルミナ女学校(現・大阪女学院)、大阪府女子専門学校(後の大阪女子大学、現・大阪府立大学)英文科卒業後、ウヰルミナ女学校英語教師となる。戦中に夫を亡くし、三児を育てながら、銀座に進駐軍向けのナオミ洋装店を開く。1951年12月、財団法人ナオミの会設立〈現在、社会福祉法人ナオミの会:本部、東京都世田谷区等々力。「ナオミ」は旧約聖書ルツ記にある未亡人の名〉。1954年、東京・世田谷に、キリスト教精神にもとづく、職業訓練のための母子寮ナオミホーム、ナオミ保育園を設立。全国初の病児保育や、産休明け乳児保育・0歳児保育等にも先駆的に取り組み、生涯を母子家庭の自立・子育て支援のために捧げた。
●再版にあたって(抄)(2025年8月 終戦の日に 遠藤久江)
ナオミの会の歴史を考える時、どうしても第二次世界大戦後の日本の姿を描きながら進めなければなりません。2025年は戦後80年目を迎え、戦争による破壊や荒廃は過去のものとなり、忘れられてきていますが、ウクライナの戦争やガザ地区での戦禍の現実が80年前の日本の姿を髣髴とさせます。1945五年の敗戦は生き残った者たちにとっては過酷な現実を生きのびるための闘いの日々の始まりでもあったのです。ナオミの会はそのような状況の中から生まれました。
今日のナオミの会は1カ所の母子生活施設、4カ所の保育園(2カ所の分園)を持つ大きな組織になりました。
ここ数十年の社会の変化には目を見張るものがあります。高度に発展した社会経済状況は人々の生活を豊かにしていますが、一方で持てるものと、持たざるものの格差を拡大させ、高度に発達しているデジタル社会は生活の利便性は高まっていますが、人間同士の感情の交流を不要とし、孤立感と疎外感を深める結果をもたらしています。
このような社会がもたらす意識の変化や生活スタイルの変化は、若い子育て世代に一番早く現われます。保育者はこの現実に向き合って親たちと協働している専門家集団です。親の子どもへの思いはさまざまですし、大事にしたい思いも多様です。この親たちと地域社会の子育てをしているナオミの会を継承しているものたちは菊田先生の歩みから大切にするべきものを見出していかなければなりません。」
■(目次より)
第一章 キリスト者の系譜
父、森田金之助と足利教会/母と友愛幼稚園
第二章 菊田澄江の生い立ち
幼少期/成人期/39
第三章 敗戦の中から
夫の死/進駐軍のお土産屋さん/ナオミ洋装店の設立/協力者たち/はじめての渡米
第四章 戦後の母たち・子どもたち
ナオミホームの構想/ナオミの会と尾山台教会/財団法人の設立/募金活動と財政活動
第五章 ナオミホームとナオミ保育園
ナオミホームのスタート/規則/ホームは火の車/ナオミ保育園の開園/乳児保育はじまる
第六章 女性の自立を支える
ナオミ保育園父母の会/病児保育の開始/バンビのあゆみ/社会的活動/ナオミ保育園労働組合
第七章 新しい皮袋
改築への取り組み/志を成し遂げて
菊田澄江年譜及びナオミの会年表
■著者紹介:遠藤久江(えんどう・ひさえ)
1938年、樺太生まれ、日本社会事業大学・明治学院大学大学院社会学研究科修了。東海大学教授、聖隷クリストファー大学社会福祉学部長、東京YWCA専門学校長を経て、現在社会福祉法人二葉保育園理事長、特定非営利活動法人 ウイメンズハウス花みずき代表、特定非営利活動法人東京YWCAヒューマンサービスサポートセンター代表、公益財団法人愛恵福祉支援財団理事、社会福祉法人ナオミの会理事他。
ご注文・お問い合わせ