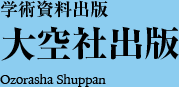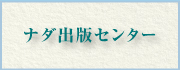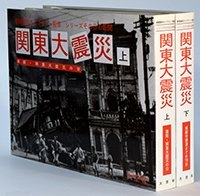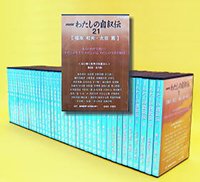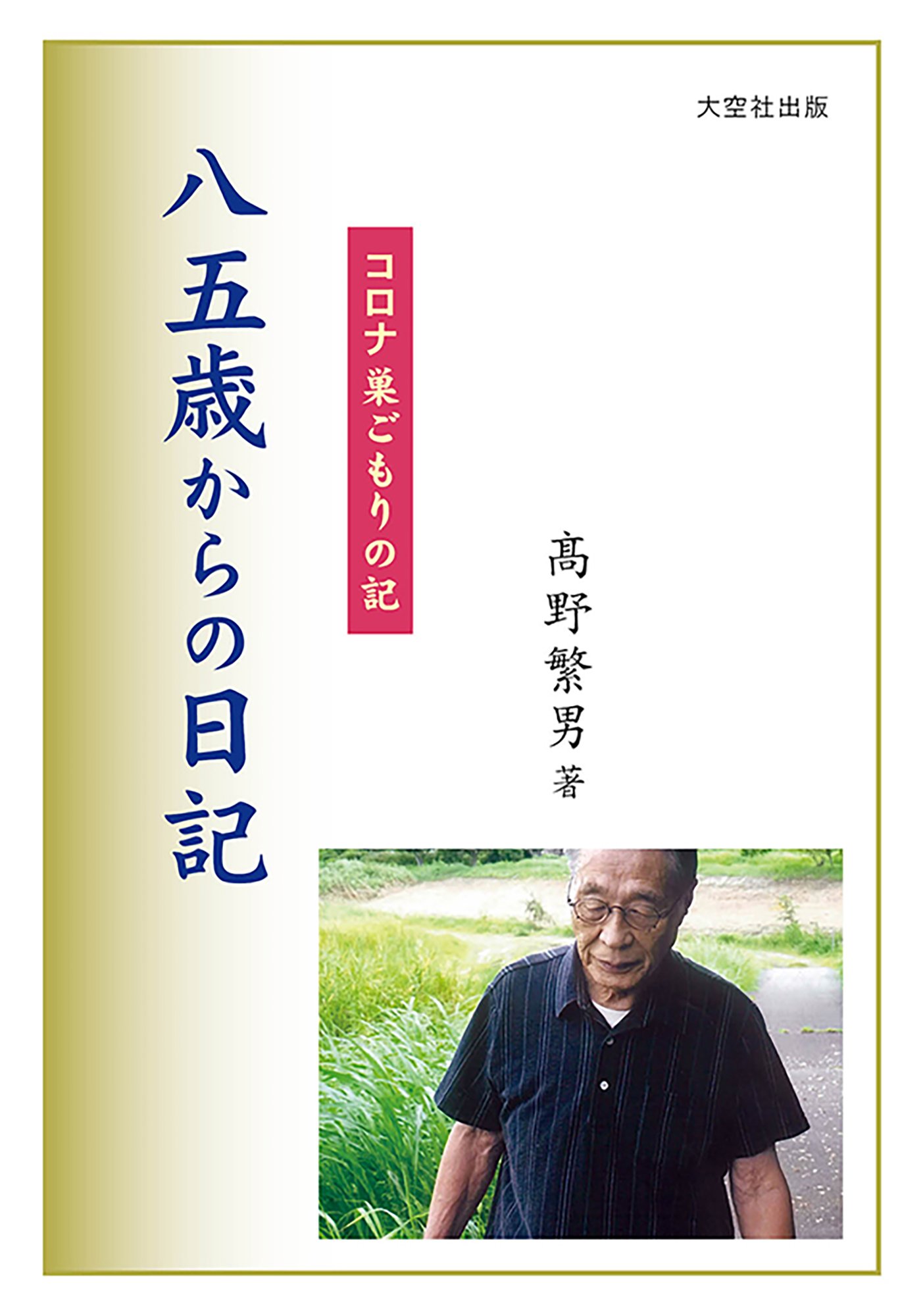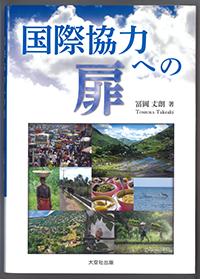社会
〈シリーズその日の新聞〉関東大震災 全2巻
発行年月:1992年8月(大空社)
1923(大正12)年9月1日 関東大震災が起きた日から2か月半後、戒厳令が撤廃された11月16日までの全国の新聞(延べ37紙)・官報等を分類・整理し収録。
関東大震災がもたらした社会の変動が、迫力の紙面から手に取るように読み取れる歴史の第一級資料。
さながら当日の新聞を手に取るような迫真の紙面【大判(297×420ミリ)。広げればA2判の特大折込を多数収録】に、生々しく惨状が展開する。現在では制作困難な貴重な蔵本。
○お断り:本の状態について○本書は刊行年が古いため(約30年前)、カバー・表紙・見返し等に経年による劣化が見られますが、本文は良好で閲覧に支障はありません。
NHK わたしの自叙伝 CD全39枚・解説書1
発行年月:(2回配本)2012年5月・10月
★「戦後80年・昭和100年」のいま、あの人たちが「自らの戦争・戦中期体験」を語る貴重な音声記録!
昭和を代表する各界の巨星78人が音声で残した生涯の核心。
政治家・実業家・事業家・社会運動家・教育者・学者・研究者・ジャーナリスト・作家・芸術家・デザイナー・演劇人・映画人・俳優・スポーツ人。現代日本のさまざまな分野で活躍し名を残す“あの人”たちが、じっくりと自らを語る貴重な音声記録。
民生委員制度の原点 岡山県済世顧問制度の通史的論究 現代地域福祉の視座を求めて
発行年月:2025年8月
「岡山県済世顧問制度は、1917(大正6)年に創設され、翌年に創設された大阪府方面委員制度と並び現在の民生委員制度の源流の一つとされている。全国民生委員児童委員連合会は済世顧問制度創設から数えて、2017(平成29)年を民生委員制度100周年としている。また済世顧問制度が公布された5月12日を民生委員・児童委員の日とし、5月18日までを活動強化週間としている。このように、現在でも民生委員制度の原点として認知されている済世顧問制度であるが、その全体像が必ずしも明らかにはされておらず、先行研究の数もそれほど多くはない。このことから、本研究では済世顧問制度の全体像を明らかにすることを第一義的な目的とした。
また済世顧問の思想や人物像、そして、その実践を検証することは、民生委員の原点にアプローチすることにもつながり、どのような過程を経て、現在の民生委員制度にたどり着いたのか、民生委員制度発祥の地とされる岡山県を事例として見て行くことにもなる。」(「はじめに」より)
一次資料から抽出構成した多数の図表を収載し、初めて制度変遷の実情を克明に跡づける労作。
反骨の新聞人 長谷川善治 昭和初年『萬朝報』での言説と行動
2025年8月
長谷川善治――戦後80年・昭和100年のいま、この知られざる「新聞人・ジャーナリスト」の“火を噴く”言説に耳を傾けよ!100年前の日本・世界は、まさに現代の引き写しだ!
★初めてなる人物伝★
明治創刊の名だたる『萬朝報』(よろずちょうほう)の再興に尽くし社会問題摘発に果敢に挑んだ熱血漢の言説と行動の真意を読み込み冷静な歴史家の目で時代の中に位置づける。同時に、弟・長谷川良信―社会事業家・教育者・浄土宗大僧正―の『萬朝報』主筆としての活躍に初めて光を当てる。著者(善治の甥、良信は父)でこそ書けた記念的論考。
八五歳からの日記 コロナ巣ごもりの記
発行年月:2024年4月
2019(令和元)年6月「八五歳からの日記」として書き始められたが、新型コロナ感染症パンデミックの襲来。「巣ごもり」の日々を過ごすなか、日記の矛先は日本の政治・社会問題を見つめ直す方向に様変わりした。「後期高齢者」の苦言に満ちたエッセイ集。
高度経済成長と社会教育
発行年月:2024年1月
戦間期・占領期に次ぐ近代日本の大きな転換期「高度経済成長期」(およそ1955~1975年)。大量消費社会で発生した諸問題、その中で諸地域で展開された社会教育の実践・理論・政策を追い、「権利としての社会教育」が追求された意味を再確認、これからの日本社会の課題解決のために新しい理論的・実践的提起を目指す。11人の研究者による共同研究。
● 紹介記事が掲載されました
・日本教育学会「教育学研究」91(4)(2024年12月)
■テーマ・論点■
1 高度経済成長期における住民の自己教育と、その政策面での展開はどのようなものだったか。
2 大量消費社会のただ中、社会教育の実践・理論はいかに当面する諸矛盾に取り組んだか。
3 「権利としての社会教育」が唱えられ追求された意味を再確認する。
4 日本の高度経済成長と社会教育のかかわりを歴史的に整理し、新興諸国の経済発展と人権保障のあり方を考える。
制度はいかに進化するか
発行年月:2022年3月
資本主義・民主主義国家の政治経済的「制度(institutions)」は、伝統的手工業者や現代的産業・企業経営者が生産力の柱として編成する「技能形成(skill formation)」システムと、いかに重要な関係を持っているか。 ドイツ・イギリス・日本・アメリカ4国の労働政策や労働運動・企業内職業訓練の実際を歴史的に比較検討、各国間の「差異」を鮮明化し、「技能」の保持・継承がいかになされたかを追究。停滞・休止・停止そして漸進・革新は、政治経済的「制度」といかなる相関関係を持つのか、多角的・重層的に分析する。 現代アメリカを代表する政治学者(現在、MIT教授)による主著。難解な原著の待望の翻訳。適宜原語を並記し、著者の意図を精確に汲み取ることに意を尽くしたていねいな翻訳。詳細な参考文献、各種索引=引用文献著者・企業・団体/組織などは研究に至便。
少年行刑の歴史からみる知的障害者福祉の萌芽
発行年月:2022年3月
(「序章」より)
近年、社会福祉専門職の職域は、従来の福祉分野にとどまらず、労働・教育・司法・保健医療等へと拡大されつつある。そのなかでもとりわけ、福祉分野と司法分野との連携・協同という古くて新しい課題が注目され、更生保護施策における新たな支援枠組みに関する検討がすすめられている。「古くて新しい」というのは、非行や犯罪に関わった人々の社会復帰に向けた援助は明治大正期にまで溯るのであり、これまでに、出獄人保護事業や感化事業など司法領域における福祉的な対応が模索されてきたということである。また、近代初頭の少年行刑・感化矯正のもとでなされた知的障害者処遇には、処罰にとどまらない保護的・教育的な視点がみられ、ここに知的障害者福祉の萌芽的状況をとらえることができる。しかしながら、これまでの知的障害者福祉研究では、当時の処遇に関する検討が十分になされたとはいいきれない。福祉と司法の連携・協同が模索される現在、福祉的な視点と司法的な視点とが未分化であった近代初頭の知的障害者処遇からは、いかなる示唆が得られるであろうか。本書は、こうした問題意識に依拠しつつ、近代初頭の少年監獄における知的障害者処遇の形成過程を解明することによって、知的障害者福祉研究の進展に貢献することを目的としている。
少年監獄における知的障害者処遇を解明するにあたり、本研究では浦和監獄川越分監を取り上げる。その理由は、川越分監では、「低能者研究」「低能者特別教授」等、知的障害者に対する処遇がいちはやく実施され、ある一定の組織だったアプローチが展開されていたためである。このことは、川越分監が我が国最初の幼年者対象の監獄として設置され、監獄改良の主眼であった懲治人教育が実験的におしすすめられていたことと深く関連している。またそうした位置づけゆえに、川越分監は「先進川越」として、全国の他の少年監のモデルともされていた。これらのことから、浦和監獄川越分監が知的障害者処遇の嚆矢として、それ以降の少年行刑にも一定の影響をもたらしたことが予想される。そうした意味から、川越分監の諸実践に焦点をあて、知的障害者処遇の起点とその具体的なありようを把握していくことは知的障害者福祉の歴史研究において不可欠な作業であると考える。
私の記録、家族の記憶 ケアリーヴァーと社会的養護のこれから
発行年月:2021年8月
◆なぜ“記録”が「社会的養護」にとって重要なキー概念なのか?
史資料の記録・保存・利活用を研究するアーカイブズ学の知見で見えてくる。“記録”にアクセスする側(当事者)/“記録”作成・管理に携わる側、双方にとって「公正・公平」な環境をいかに構築するか、施策はどうあるべきか……。
◆ケアリーヴァー care leaver のための“記録 records”への安定したアクセスを目指して、現状の課題を明らかにし、将来へ向けての提言を示す。社会福祉・社会事業分野とアーカイブズ学との有機的連繋、初の成果。
●世界(イギリス、オーストラリア、韓国)は、日本は? 考える第一歩に本書をまず手にとってみてください。社会事業・福祉、児童養護等に関わる組織・団体・施設・行政関係から研究者まで、じわじわと読者が広がっています。
国際協力への扉
発行年月:2021年4月
国際協力に携わって35年、アジア、アフリカ、中南米での豊富な経験を「すべての人へ」!
自身の経験を具体的に語り、協力活動の基礎情報・知識をテキスト形式にまとめた実践・準備編からなる。
SDGsなど、若い人たちだけでなくなった現代の教養=国際協力(開発協力)への好入門書。