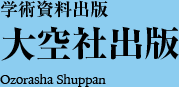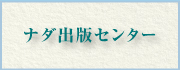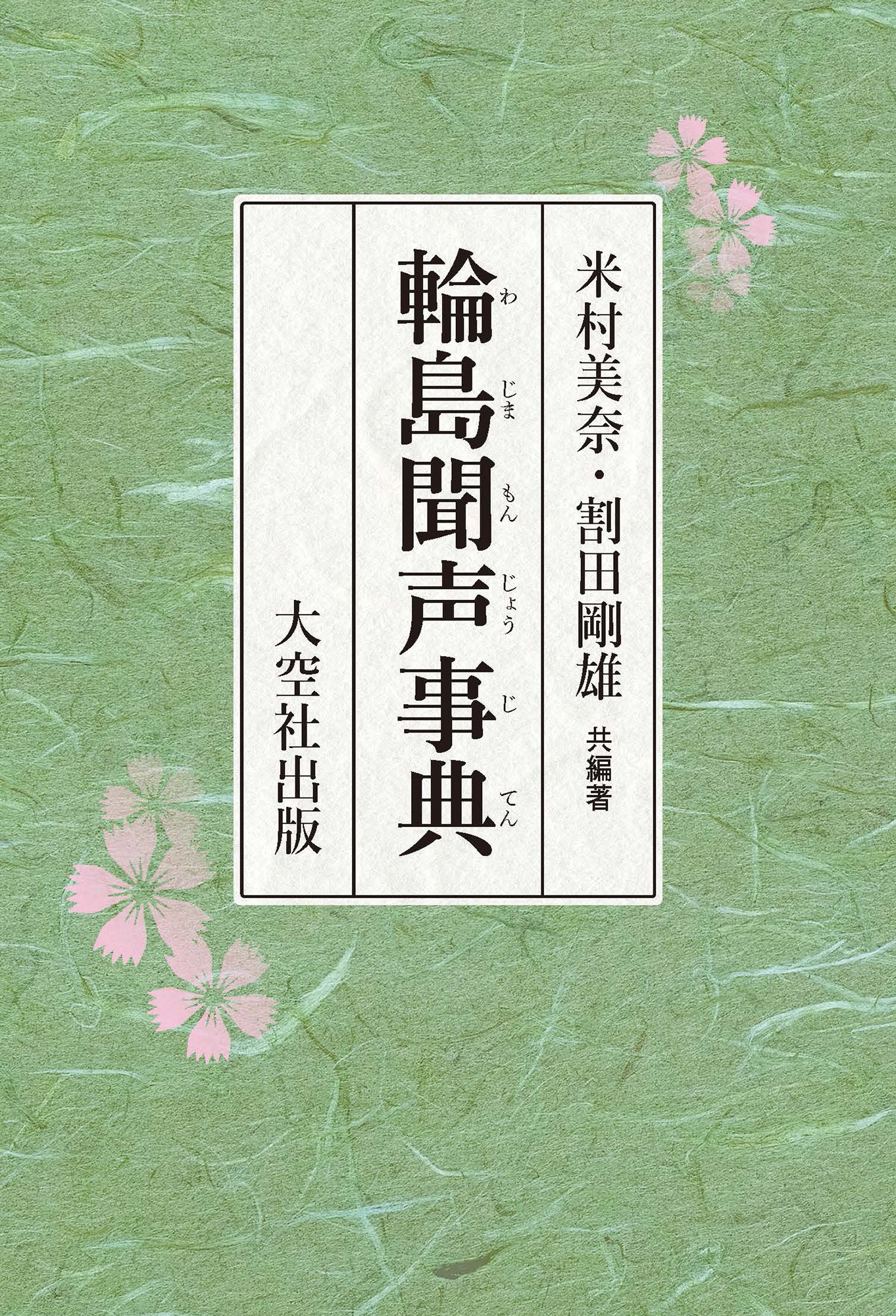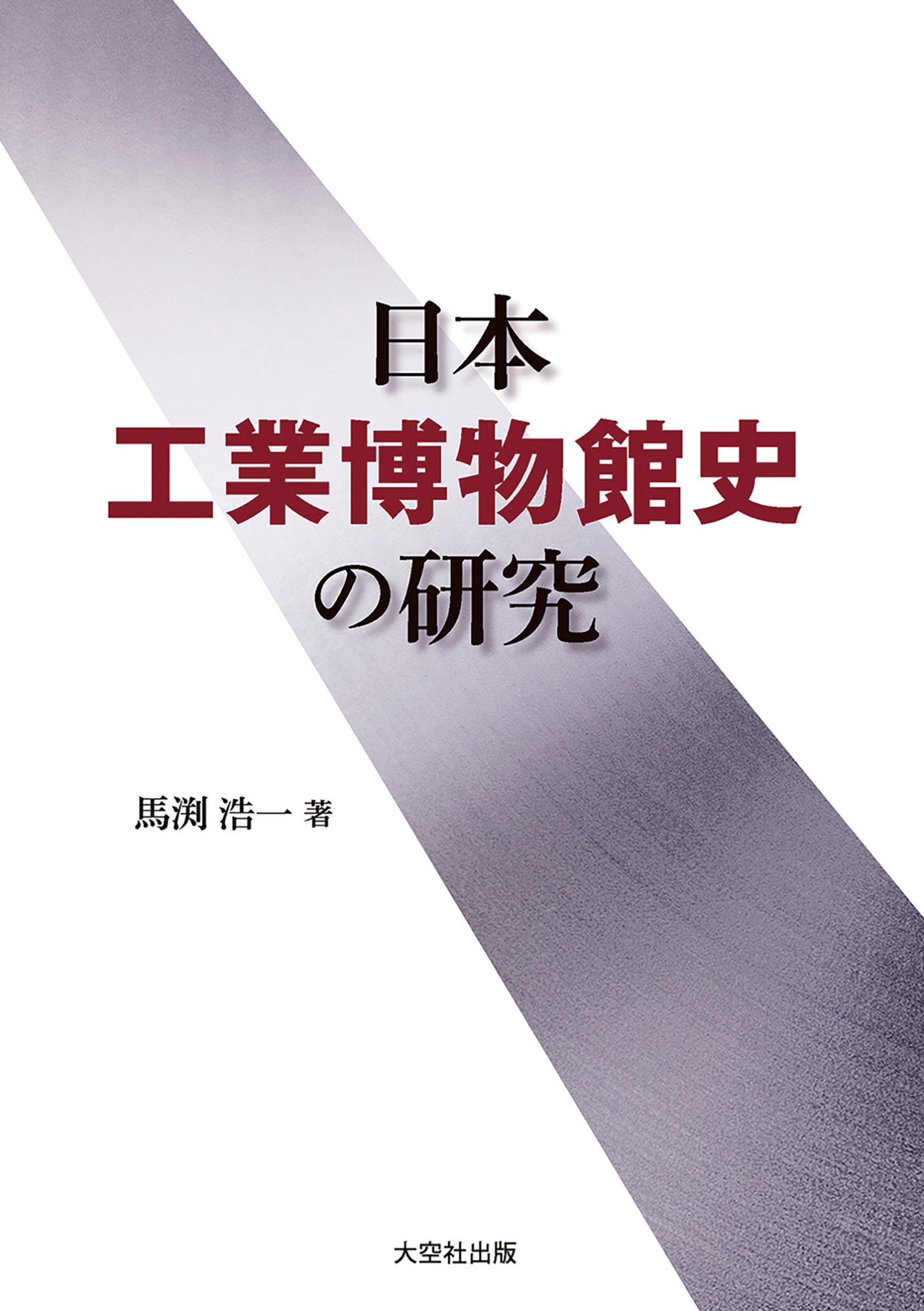教育
看護・保育・福祉・教職課程のためのセクシュアリティ論ノート
発行年月:2025年4月・修訂3刷
“人間の性:ヒューマン・セクシュアリティは人間が生きる事そのものである”
対人援助の職種(看護・保育・介護・教育など)を目指すすべての人が、「セクシュアリティ」に関する「知識と介入スキル」の基本を習得するためのテキスト。永年の教授経験から生み出された事例をもとに学び、考える、実践的な書。この分野では数少ないテキスト。
近年大きな議論となっている包括的性教育やLGBT に代表されるセクシャルマイノリティに関する既述個所を加筆修訂した。
輪島聞声事典
発行年月:2024年3月
大乗淑徳学園の校祖・輪島聞声〈わじま・もんじょう〉(1852-1920)。震災・戦災などで資料が僅かしか残されない状況下、その足跡を訪ね歩き丹念に取材を重ねて得た厖大な史料をもとに、師の生涯と思想を浮き彫りにする。関連人物・社会背景・文献などの大・中項目を情報源として、聞声自身の声・姿に近づくユニークな事典形式を採用、貴重図版を多数収載する。
高度経済成長と社会教育
発行年月:2024年1月
戦間期・占領期に次ぐ近代日本の大きな転換期「高度経済成長期」(およそ1955~1975年)。大量消費社会で発生した諸問題、その中で諸地域で展開された社会教育の実践・理論・政策を追い、「権利としての社会教育」が追求された意味を再確認、これからの日本社会の課題解決のために新しい理論的・実践的提起を目指す。11人の研究者による共同研究。
● 紹介記事が掲載されました
・日本教育学会「教育学研究」91(4)(2024年12月)
■テーマ・論点■
1 高度経済成長期における住民の自己教育と、その政策面での展開はどのようなものだったか。
2 大量消費社会のただ中、社会教育の実践・理論はいかに当面する諸矛盾に取り組んだか。
3 「権利としての社会教育」が唱えられ追求された意味を再確認する。
4 日本の高度経済成長と社会教育のかかわりを歴史的に整理し、新興諸国の経済発展と人権保障のあり方を考える。
日本工業博物館史の研究
発行年月:2023年10月
明治以降、幾度となく提案されてきた日本の工業博物館設立計画、しかしいまだ実現されないのはなぜなのか?近代日本の博物館の歴史に刻まれる“工業博物館”構想に関わった官民・学術・教育の人々の営為を、厖大な史料文献・データを的確に整理し、鋭く歴史の核心に迫る。永年、博物館業務に従事してきた著者だからこその視点で書かれたユニークな業績。各種変遷・概要・分類・数量データから組織・人物略歴・社会背景を明解に提示する有益・豊富な図表54点を収載。読みやすい・明解な文章。
制度はいかに進化するか
発行年月:2022年3月
資本主義・民主主義国家の政治経済的「制度(institutions)」は、伝統的手工業者や現代的産業・企業経営者が生産力の柱として編成する「技能形成(skill formation)」システムと、いかに重要な関係を持っているか。 ドイツ・イギリス・日本・アメリカ4国の労働政策や労働運動・企業内職業訓練の実際を歴史的に比較検討、各国間の「差異」を鮮明化し、「技能」の保持・継承がいかになされたかを追究。停滞・休止・停止そして漸進・革新は、政治経済的「制度」といかなる相関関係を持つのか、多角的・重層的に分析する。 現代アメリカを代表する政治学者(現在、MIT教授)による主著。難解な原著の待望の翻訳。適宜原語を並記し、著者の意図を精確に汲み取ることに意を尽くしたていねいな翻訳。詳細な参考文献、各種索引=引用文献著者・企業・団体/組織などは研究に至便。
「劣等児」「特別学級」の思想と実践
発行年月:2021年5月
教育と思想、教育と政策・制度、教育と社会。その中の児童と家庭と、目の前の現実に正面から立ち向かう教師たち…。
“奈良県”から見えてきた、大正末から昭和初期日本の教育“現場”の実態を、一次資料で浮き彫りにし、課題を鮮明化する。
近代日本教育史の一隅に響く、思想と実践の相克を、丁寧にたどって見えてきたものとは…。
「劣等児(学業不振児)」のための「特別学級」は、過去の〈終った〉歴史ではない。
京都「特別学級」成立史研究―史料と論究
発行:2021年2月
「特別学級」その発想の端緒は? 設置と運営を担った人々の模索と苦闘の跡を語る、稀有な史料を一挙復刻し辿る、初の京都「特別学級」実践概史。
明治期から障害児者の教育・保護事業に先駆的に取り組んでいた地、京都――戦前戦中期に「特別学級」の設置と実践を旺盛に展開したのも京都だった。小学校・児童の「特別学級」実践と模索を跡づける、現場を担った教師や京都市関係者の残した稀少で貴重な史料を一堂に会し、その意義を確認し、後世への遺産として復刻する。
近代社会教育における権田保之助研究 娯楽論を中心として
発行年月:2019年8月
「民衆娯楽研究の第一人者」権田保之助 を「社会教育」の観点から読み直す。
大原社会問題研究所所員、文部省・厚生省専門委員嘱託として、関東大震災を挟み大正から昭和戦中期、数々の娯楽調査・社会調査(家計、労働、農村、学生、映画、月島・浅草等々)に関わり、今日に残る実証的研究・記録を残した。
「娯楽は本来「民衆主体」の生活創造としてある」
「「民衆娯楽」は権力が政策として方向付けるものではない」
「(震災からの)復興のバロメーターを民衆の娯楽要求に見る」
権田保之助の“仕事”への好案内。再読のために、初めて読むときに。多岐にわたる権田の著作群から、できるかぎり自身の用語・表現で語らせる形で構成し、権田の意図・真意を丁寧に辿った。
学校体育におけるボールゲームの指導理論に関する研究 フラッグフットボールを中心にして
発行年月:2018年3月
「本書は、わが国の学校体育の中で、ボール運動系、特に「ゴール型」ゲームの指導の変遷をたどり、それぞれの時代における意義と課題を明らかにしながら、現代の学校体育授業におけるフラッグフットボールの指導内容を、その文化的・歴史的背景にもとづいて理論的に構築することを試みたものである。」(まえがきより)
日本における女子体育教師史研究
発行年月:2018年2月
日本近代史・教育史に新たな視点で今日的課題に迫る大著
同じ女子教師であっても、女子体育教師のみが女子教師からも体育教師からも差異化されてきた理由は何か? 男女共修・男女共同参画時代における女子体育教師の役割をどのように位置づけるか
女子体育概念、女子体育教師像、教師養成機関の変遷等、女子体育教師の歴史と現状を厖大なデータをもとに詳細に跡づけ分析・考察し、今後の女子体育教師のあり方を考える基礎資料とする。
明治初期から現代に至る日本における女子体育教師史の全体像を体系的に明らかにした初の研究。
*統計・調査記録・年表等 図表約250点収載