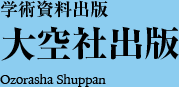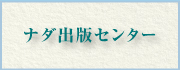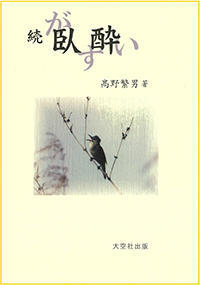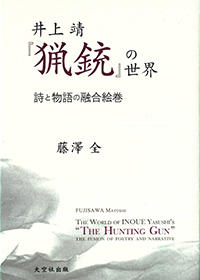ことば・文学・芸術
「翻訳詩」事典 フランス編
発行年月:2018年7月
“詩の翻訳”は翻訳の可能性を追求する本道
明治以降の「翻訳詩」の深奥で馥郁たる文学世界を、厖大な原典引用(作品・試論と翻訳者・原作者)で鳥瞰し、見せる、真にユニークな“初の”事典。
詩を詩歌を読む、日本語をより深く味わうとき、つねに携えたい“新”文学事典。
近代日本の詩人・作家・批評家にとって、“詩とは何か”ということは“詩の翻訳とは何か”に等しかった。しかし…
「翻訳詩の地位は、その歴史的役割の大きさに比して、あまりに低い」(刊行にあたって より)
文明開化の歌人たち 『開化新題歌集』を読む
発行年月:2017年12月
『開化新題歌集』(1-3編)は明治10年代出版の出題歌集(大久保忠保編)。
そこからは明治初期、激変期日本人の驚き、衝撃、哀歓、興味、感動が、情感豊かに伝わってくる。
押し寄せる西洋の新奇事物、歴史の波涛に揺られながら、歌人たちは何を感じ歌ったのか。
現代を生き、詠む歌人が、彼らの生涯と時代を丹念に追い、作品と時代の心を味読する。
続 臥酔〔がすい〕
発行年月:2017年11月
日本語研究に従事してきた学者が、歴史・自然・ことばについて、旅を日常の体験を、取材し、追憶し、思うこと、言わずにいられないことを、ときに批評し書きとめる。戦後70年、中国、モンゴル、北海道、善光寺、野鳥、日本語の宇宙観…。写真全点カラー。
みだれ髪
発行年月:2017年4月
“やは肌のあつき血汐に…” 明治34年刊の処女歌集(鳳の名で刊行。装幀・挿画:藤島武二。東京新詩社・伊藤文友館刊)を原本装幀にならい忠実に複製(表紙・挿絵他フルカラー)。
井上靖『猟銃』の世界 詩と物語の融合絵巻
発行年月:2017年4月
多くの外国語に翻訳され映画・演劇化される短篇『猟銃』。
不惑四十を過ぎて新聞社デスクから文壇へと鮮烈なデビュー(1949・昭和24年「文学界」)を遂げた井上靖(1907~91)。
その記念碑的作品の機構=作立てに込められた詩と物語の香気に満ちた芸術的源泉を精緻に紐解きながら、作品=ロマンの主題と魅力をあぶり出す。
伝記・研究の第一人者が文芸作品を堪能する醍醐味へと誘う渾身の名作ガイド。
〈生誕110年記念出版〉
近代日本語史に見る教育・人・ことばの交流 日本語を母語としない学習者向け教科書を通して
発行年月:2017年3月
日本語を母語としない(日本語を外国語とする)学習者向けに作られた近代の〈日本語教科書〉には、どのような〈近代日本語〉の姿が刻まれているのか? “近代日本語”をあまり取り上げられない資料から照射し、日本語史研究に新たな知見を提示する。
アジア学叢書 347巻 標準マライ語文法
発行年月:2021年4月
原本:南洋協会、1943・昭和18年刊。
〈自序〉今更云ふ迄も無く南洋一帯の通用語はマライ語であるが、既述の通り其の使用人口数が7千万余であると言ふ事実を見ただけでも、之が一つの立派な国語であり非常な重要性を持つものであると言ふことが容易に判断出来るのである。勿論今日迄既に幾多先覚者に依りて其の必要は叫ばれ、多くのマライ語に関する書籍等も出版せられて居るが、之は一般外国語の如く未だ充分普及せられて居らず、概して翻訳的なものが多く権威ある参考書等入手困難であつた。
アジア学叢書 346巻 馬来語広文典
発行年月:2021年4月
原本:岡崎屋書店、1940・昭和15年刊[使用底本は昭和17年三版]。
〈自序〉私は大正11年4月東京外国語学校馬来語科に入学して、恩師上原訓蔵先生について馬来語の手ほどきを得、今日まで一ト時も馬来語とは離れた事がない程専ら馬来語研究に身も心も打込んで来た気儘者であるから、勢ひ講述の態度が不遜である様な事もあるかも知れないが、何卒寛大なる襟度を以て赦して頂き度いのである。
アジア学叢書 345巻 最新 馬来語教本 附 馬日・日馬・小辞典
発行年月:2021年4月
原本:新正堂、1942・昭和17年刊。
〈自序〉 最近しきりに、日本語化政策が喧伝されるが、これこそ最も注意を要する仕事でなければならぬ。抑々南方圏の言語構成現状は、英語、和蘭語、支那語、マレー語等であるが、マレー語こそは、最も尊重に値する言語である。マレー語は東印度、馬来半島一帯の土著語に最も近く、又同時に共通語である。政府当局は占領地一帯の土著語を尊重する旨声明してゐるが、これこそ時宜を得た政策と云ふべく且インドネシア民族を尊重するものと云ふべきである。〔…〕マレー語は南方圏の共通語であるし、マレー語修得こそは南方開発の最大武器たる事は多言を要せずして明かであらう。
アジア学叢書 344巻 実用馬来語辞書
発行年月:2021年4月
原本:花屋商会書籍部、1927・昭和2年刊。
〈序 井上雅二〉 従来、巷間に見る此種の著書は、海峡植民地々方に行はるゝ馬来語を基本とするもの多く、蘭領方面に業を従はんとするものには、必ずしも適切と評し難き憾あり、此時に当り、此の有用なる良著を公にせらる、蓋し其恵に浴する者、多かるべく、同君の此著ある、亦此辺に鑑みる所あつての事と信ずるのである。